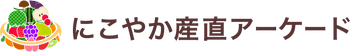メロンの特徴・保存方法等
【特徴】
英語名:melon ウリ科キュウリ属

流通や食生活の分類や栄養学上は果物としています。原産地は東アフリカから中近東と言われています。
表面に網目がでるものと出ない物があり、両者を掛け合わせた品種などもあります。
また、果肉の色の違いによって夕張メロンなどの赤肉系、アンデスメロンなどの青肉系、ホームランメロンなどの白肉系があります。栽培方法も三種類あり、温室メロン、ハウスメロン、露地栽培があり、出回る時期は様々です。
【時期】
多く出回る時期は様々ですが、一番多く出回るのは4月~9月頃です。
産地 都道府県ランキング
1位 茨城県
2位 熊本県
3位 北海道
4位 山形県
5位 青森県
【歴史】
メロンは古代エジプトや古代ギリシャの頃から栽培されていました。暖かい地方でしか栽培できないため、北ヨーロッパなどで栽培されるようになったのは14世紀以降と言われています。日本ではメロンの仲間のマクワウリが弥生時代から栽培されていたようで、その頃の遺跡から種が発掘されています。温室メロンが栽培されるようになったのは大正時代になってからです。
【選び方】
編みありメロンの場合は編みの起伏がはっきりしていて細かく均一に広がり、丸実がきれいで傷がないものを選びましょう。編みなしメロンの場合は果皮の色が均一で丸みがあり、持って重みのあるものを選びましょう。
【保存方法】
完熟していないメロンは常温で追熟させてから食します。食べる2~3時間前に冷蔵庫へいれて冷やしましょう。冷やし過ぎると味が落ちるので注意が必要です。熟して食べごろになると甘い香りがして、尻の部分に少し弾力が出てきます。収穫日から1週間くらいまでが追熟の期間です。
【栄養素】
メロンは果物の中でもカリウムの含有量が多く、ビタミンやミネラル、食物繊維も豊富に含まれています。
【カリウム】カリウムは塩分を排泄したり、水分バランスを整えたりする働きがあり、むくみの改善、腎臓病や高血圧の予防に効果があります。
【βカロテン】赤肉メロンにはβカロテンが含まれていて、抗酸化作用があると言われています。
【薬効】
ウリ科の食べ物は体内の水分を調節し利尿作用を促す働きがあります。そのため、尿が出にくい時に用いたりします。
【種類】
アンデスメロンや夕張メロン、アムスメロンやプリンスメロンなど、多くの品種があります。
【果皮に網目のある品種】果皮に細かい網のあるメロンで、大きさは小ぶりで果肉は緑色です。ハウス栽培が主流で、アンデス山脈とは関係が無く「安心ですメロン」という名前からアンデスメロンへ変化したといわれています。
【マスクメロン】高級メロンの代表といわれるメロンで、ムスクの香りがすることからこの名前がついています。
【北海道の品種】果肉がオレンジ色で甘みと果汁が多く人気がありますが、日持ちしない品種です。
【プリンスメロン】サイズは小さめで果皮に網はなく、果肉の薄緑色のものとオレンジ色のものがあります。