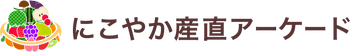りんごの特徴・保存方法等
【特徴】
英語名:apple バラ科リンゴ属 落葉小高木

人間誕生の物語アダムとイブにも登場するほど昔から存在する果物です。コーカサス地方が原産地で、日本に出回っている75%が青森や長野などの国産品種です。生食やジュース、ジャム、製菓などに利用しています。
【時期】
旬として出回る時期は9月~1月ですが、AC貯蔵(庫内空気の二酸化炭素を増やし、低温状態で保存する方法)により、1年中鮮度のあるリンゴが出回っています。
【歴史】
リンゴは紀元前6000年ころのトルコから始まって、紀元前1300年ころにはエジプトで栽培されていたといわれています。日本で栽培されるようになったのは明治以降で、日本の風土に合わせた品種改良が行われ、多くの品種が出回るようになりました。
【選び方】
リンゴは軸が太くて果皮に張りとツヤがあるものを選びましょう。赤いリンゴは果皮が十分に赤く染まり、下の部分が黄色いものが熟しています。尻の部分が緑色のリンゴは未熟の可能性があります。品種にもよりますが、大きすぎる物よりも中くらいのリンゴの方がよく、持って重みのあるものがよいです。果皮の赤みのまだらや傷は見た目が良くありませんが、味と糖度に影響はありません。また、リンゴの表面がぬるぬるしている場合がありますが、そのぬるぬるしたものはワックスや防カビ剤などではなく、リンゴの成分により生成したものです。
【保存方法】
リンゴは水分の蒸発を防ぐために新聞に一つずつ包んでビニール袋などに入れ、冷蔵庫か涼しい場所で保存します。低温高湿度で保存してもあまり日持ちしないので、早めに食べきりましょう。リンゴは植物ホルモンのエチレンを発して、他の果物や野菜の成熟を促してしまうので、冷蔵庫や段ボールに入れる際には、個別に包み、袋に入れて保存しましょう。
【栄養素】
約85%が水分で、栄養成分としてはビタミンC、カリウム、水溶性食物繊維のペクチンなどが豊富に含まれています。また、ポリフェノールのカテキンろケルセチンじには様々な病気の予防に効果が期待され、昔から「1日に1個のリンゴは医者を遠ざける」と言われています。
【食物繊維】水溶性の食物繊維は消化促進や胃酸のバランスを整える働きがあります。またコレステロールの排出や急な血糖値の上昇を防ぐ効果があります。
【カリウム】リンゴには栄養素ミネラルのカリウムが多く、塩分を調節して高血圧を予防したり、肝臓の老廃物の排出を促したりする役割を担っています。
【ポリフェノール】ポリフェノールの一種のカテキンには抗酸化作用があり、高血圧の予防に効果が期待され、ポリフェノールの一種のケルセチンには動脈硬化があるといわれています。
【薬効】
中国の薬学著書である「本草網目」に、リンゴは閃癖(下痢と引き攣りで全身が痩せ衰える病)に効果があると記載されています。下痢や免疫力の回復などの効果がある反面、食べ過ぎると熱が出たり、脈が弱まったりするとされています。
【種類】
世界では25000種以上の品種が報告されています。
【一般的な品種】酸味が少なく甘みが強く果実が大きめなのが特徴です。果汁が多く、蜜入りのものは甘く人気があります。
【青りんごの品種】果皮が黄色で酸味が少なく甘く独特の香りがある品種です。果皮にサビのあるものは見た目が劣りますが味はよいといわれています。
【アメリカで交配した品種】ゴールデンデリシャスと紅玉を交配して誕生したリンゴで、紅玉のような酸味があり、シャキシャキとした食感のある品種です。
【酸味のある品種】アメリカで発見された「ジョナサン」と同じ品種です。酸味が強く多汁で、果肉がしっかりしていて、煮崩れしないので、アップルパイなどの製菓によく使用されます。