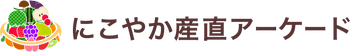柿の特徴・保存方法等
【特徴】
英語名:persimmon カキノキ科カキノキ属 落葉高木

原産地は中国です。品種は1000種以上ありますが、大きく甘柿と渋柿に分かれます。果肉は生食するほか、干し柿や菓子に使い、柿の葉も和菓子やお茶に利用します。
【時期】
多く出回る時期は9月~12月です。
【歴史】
柿は中国や、朝鮮半島、日本が原産です。奈良時代のものとして出土した木簡に柿の字が記されています。また、古事記にも柿の字が記され、昔話にも多く登場することから、伝統的に日本では食していた果実です。栽培も盛んですが、庭に柿の木がある家も多く、季節には柿をもいで食します。
【選び方】
柿のヘタがきれいで張り付くように隙間なく4枚揃っていて、緑が残っているもので、果皮が濃いオレンジ色に色付き形が整っていて、持った時に重みを感じ、柔らかすぎないものを選びましょう。品種によっては葡萄のブルームと同じ白い粉をつけるものもあり、ついていたほうが甘い品種もあります。
【保存方法】
ビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存すれば1週間ほどは保存できます。常温だと2日ほどで柔らかくなります。追熟の必要はないので、早めに食べましょう。また、ヘタの上に湿らせたコットンを置き、ヘタを下にして野菜室で保存すれば2~3週間は保存できます。やわらかくなった柿は冷凍庫で保存してシャーベットのようにして食べることができます。
【柿の渋抜き方法】
渋柿の原因はシブオールというタンニンが水に溶ける状態になっているためです。柿の果実にゴマのように固まっている黒いものがタンニンで、固まってれば甘柿になります。渋柿には加温法や炭酸ガス法やアルコール法などがあります。
【加温法】40度のお湯に12~24時間浸けます。鹿児島では温泉に一晩つけて脱渋する方法があり「あおし柿」と呼ばれています。
【アルコール法】柿のヘタの部分を焼酎などのアルコールにつけて1週間ほどビニール袋の中に密閉しておきます。
【炭酸ガス法】ドライアイスなどで炭酸ガスを発生させ、90%濃度の炭酸ガスの中に24時間密封する方法です。
【栄養素】
柿にはビタミンCやβカロテン、カリウムなどが豊富に含まれています。
【ビタミンC】果物の中ではトップクラスの含有量です。柿1個に一日に必要なビタミンCの量が含まれているそうです。ビタミンCには風邪の予防や美肌効果があります。
【βカロテン】抗酸化作用のあるβカロテンの他にカロテノイドの一種βクリプトキサンチンが多く含まれています。
【カリウム】塩分を体外へ排出する働きがあり、高血圧に効果があります。筋肉の痙攣を防ぐ効果もあります。
【薬効】
柿は血中アルコールの酸化を促進します。干し柿は、胃潰瘍や子供の下痢に良いといわれ、干柿の表面をふいた白い粉を集めたものは咳止めの効果があります。そして、柿のヘタはシャックリ止めの妙薬です。また、柿葉には抗酸化作用があるので、柿の葉寿司に使います。柿葉のお茶にはビタミンが豊富に含まれ、美容や血流のバランスをよくする作用があります。
【種類】
柿の種類には1000種近くあります。その中の甘柿は20種ほどです。甘柿の代表的な品種は富裕柿で、渋柿では平核無柿が有名です。他に刀根早生、甲州百目、次郎などが知られています。
【完全甘柿】市場の半数以上はこの品種です。ふっくらとした丸みがあり、果皮はオレンジ色で果肉がやわらかくて甘みが強いのが特徴です。
【種なし柿】種が小さくなった柿として市場に出回る品種です。不完全渋柿ですが、出荷時に渋抜きを行い、甘く口上りがよいので人気があります。
【平核無柿の改良種】出荷が早くハウスで栽培されたものは7月ころから出荷されます。渋柿ですが渋抜き後は甘みが強く、見た目は平核無と同じように見えます。
【山梨県や福島県の品種】釣鐘形の大き目の品種で不完全渋柿です。あんぽ柿や干し柿に利用されます。
【福島県原産品種】背が低く四角張った円形の完全甘柿です。歴史が古く江戸時代から栽培されています。